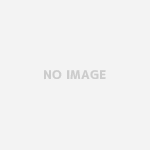今はむかし、御内に召しかかへられし野夫医者のありけるが、名をば通斎といふ。
物も知らず、只聞書ばかりにて療治をする。
その書物はみな仮名書きなり。
浮世房問ひけるやう、
「其方は学文よくさせられたそうな。
しかも療治もよくめさるると見えた。
きどくの事かな。
医学正伝は誰の作ぞ」
と問ふ。
もとより見たる事もなければ、
その作者は聞きたるばかり也。
聞書のはしに「ごうとくらうじん正でんをつくる」と、
仮名に書きて置きたるを思ひ出だして、
『それこそ存じたれ。
正伝は唐の後藤九郎二郎といふ人の作ぢや』
と答へた。
(浅井了意(あさいりょうい)『浮世物語(うきよものがたり)』による。)
現代語訳
今は昔、家臣として召し抱えられていた野暮な医者がいた。その名は通斎といった。
彼は医学知識を知らず、ただ誰かの話を聞いて書き記したものだけで治療を行っていた。
その書物はすべて(漢字ではなく)仮名書きだった。
浮世房(という坊主、浮世物語の主人公)が(通斎に)尋ねた。
「あなたは学問をよく修めていると聞いています。
それに治療もお上手だと見えます。
ご立派なことです。
医学正伝は誰の作なのですか」
と問うた。
(通斎は)元々(医学正伝を)見た(読んだ)こともなく、
その作者も聞いたことしかなかった。
聞き書きの端に「ごうとくらうじん正でんをつくる」と、
(漢字ではなく)仮名で書いておいたのを思い出して、
「それなら知っている。
正伝は唐の後藤九郎二郎という人の作だ」
と答えた。
(正しくは「恒徳老人」なのに、「後藤九郎二郎」という名前だと誤解し、
しかもそれを、さも初めから知っていたかのように、知ったかぶりをして答えた、
ということ)
※医学正傳は、中国の医学書。
作者は虞摶(ぐたん)で、恒徳老人(こうとくろうじん)と号した。
1531年、明朝時代の書。