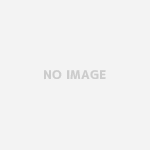子育てには女性の力が欠かせないと思います。
子育てには男性の力も欠かせないと思います。
「子育ては女の役割だと言いたいのか!?」と心がザワついた方は、「書かれていないこと」を読み取っておられませんか?
冗談はさておき、タルムードについて気付いたことがあるので書き残しておきます。
タルムードは親から子に語り継がれる物語と、「どう思うか」という問いかけを組み合わせた教育方法です。
ある動画で「正直な仕立て屋」という話が紹介されていました。
それは次のような話です。
その町の長老がある晩、不思議な夢を見ました。その夢の中で神様がこうおっしゃったのです。「次の休みの日に、町の仕立て屋に祈らせなさい。そうすれば雨を降らせよう。」朝、目が覚めた長老はその夢を思い出しましたが、「仕立て屋はお祈りの言葉を知らない。本も読めない。それなのに、どうしてお祈りをさせられるのだろうか。」と、夢を信じませんでした。そして、お祈りをちゃんと覚えている人に頼んで雨乞いをさせました。でも、雨は全く降りませんでした。
1週間後、長老はまた同じ夢を見ました。その後さらにまた、同じ夢を見てしまいました。とうとう3回目です。長老は、「これだけ同じ夢を見るのなら、やはり神様のお告げに違いない。」と観念し、町の仕立て屋をお祈りの台に招きました。
仕立て屋はお祈りの言葉も作法も知らず、ただ自分の言葉で神様にお祈りをしました。彼はいつも使っている巻尺を手に取り、こう言いました。「神様、私はこの仕立て屋の仕事を40年も続けていますが、今まで一度もお客さんをだましたことはありません。この巻尺を見てください。一寸の狂いもなく正確で、この巻尺を正しく使って仕事をしてきました。他の仕立て屋の中には、巻尺の目盛りをごまかして生地を多く売ろうとする人もいますが、私はそんなことはしません。小麦粉を売るお店や、油を売るお店でも、秤をごまかして、少ない量を同じ値段で売ったり、悪い事をしている人がいます。でも私はいつも、まっすぐお客さんと向き合って商売をしてきました。どうか、この私の正直な心に免じて、雨を降らせてください。」
その瞬間、空に雷の音が響き渡り、みるみるうちに雲が広がり、大粒の雨が降り始めました。その雨で畑は潤い、家畜たちも水を飲むことができて、町は再び元気を取り戻しました。
これを見た町の人々は、自分のお店に戻り、巻尺や量りをきちんとしたものに変えました。これを見た神様はとても喜び、この町には毎年ちゃんと雨が降るようにしてくださいましたとさ。
おわり。
この物語からは、いくつかの教えが読み取れます。
・正直であることの大切さ
・ごまかし方を教えることで、その見抜き方に対する示唆も与えること
・天網恢恢疎にして漏らさず
・雨が天の恵みであること
・人間の力ではどうしようもないことが、起こり得ること
・祈りは心であり、作法ではなく、学の必要なことではないこと
・学は必ずしも真実や誠実とは直結しないこと
・思い込みは、思い込みではないかと自ら疑い、自らを自らで省みて気づく必要があること
・祈りは祈りの方法を学んだものが行うものだ、などの固定観念の破壊も、時には必要であること
・作物は雨の恵みにより支えられていること。
・三度目の正直
・たとえそれが拙くとも、自分の言葉で語ることの大切さ
・他者が不正をはたらこうとも、自らを律することの大切さ
・正しい秤、正しい定規が、互いの為になり、町の発展に寄与すること
・商売ではお客さんを騙すようなことはしない方がよいだろうということ
・人々は結局結果を見て動く、ということ
・結局、神が監視していなければ、また不正が行われる可能性があること
・正直な仕立て屋、と見做すことができるが、他の商売人を悪く言う必要は本来なかったのではないか、ということ
(これは、集団心理に対する見せしめのような効果を期待している可能性があり、丁寧に考える必要がある)
などなど
1つの話なのに、かなり多くの切り口や示唆を含んでおり、夜、子供たちが親に物語をせがむその素朴な瞬間を、その辺の学習塾がみんな倒産するような学びの時間に変えてしまう恐ろしい教育法です。
そして今回この記事を書くに至った想いはもう一段奥にあります。
この教育法に気付き、明確に形を持たせ、この教育法そのものを伝播させ、物語数を増やすよう設計し仕向け根付かせた人々が、この「タルムード」という教育法を代々受け継ぐ民族の祖先に居る、ということです。
お気づきでしょうか。私たちの究極の仕事は、その「祖先」となるような、次世代の日本人を教育により生み出すことです。
「人を育てる、人を育てる、人を育てる」
これは
「人を育てる人、を育てる人、を育てる」と切るのが正しい。
一新ゼミの大方針です。よろしければご賛同ください。